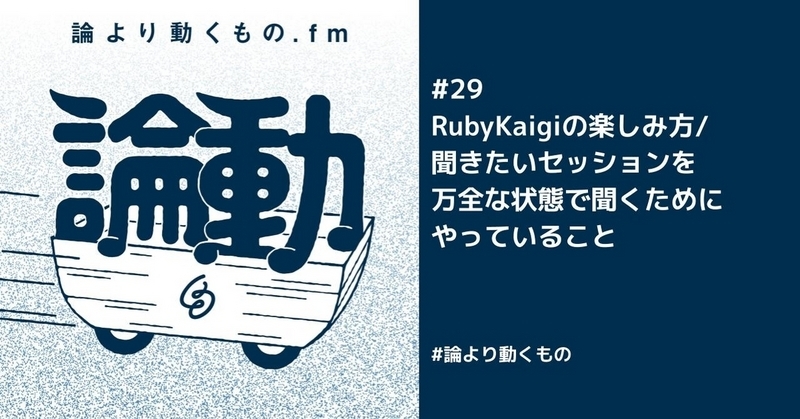
CTO 藤村がホストするPodcast、論より動くもの.fmの第29回を公開しました。今回は STORES に24卒で入社したエンジニアのmaseとRubyKaigi 2024を楽しむ方法について話しました。
論より動くもの.fmはSpotifyとApple Podcastで配信しています。フォローしていただくと、新エピソード公開時には自動で配信されますので、ぜひフォローしてください。
テキストで読みたい方は下記からご覧ください。
マニキュアはプラモデルより難しい
藤村:こんにちは、論より動くもの.fmです。論より動くもの.fmは、STORES のCTOである私、藤村が技術や技術じゃないことについてざっくばらんに話すPodcastです。今日はこの春に入社したばかりのmaseさんに来てもらいました。maseさん、こんにちは。
mase:こんにちは。
藤村:自己紹介をお願いします。
mase:24卒で STORES に入社しましたmaseです。 STORES 予約 の開発に携わっています。8月からアルバイトをしていたんですけど、あんまり日数が多くなかったというのもあって、先週から本格的にチームに入って開発をしてます。*1
藤村:よろしくお願いします。
mase:趣味はセルフネイルをすることと、姪を遊ぶことだったんですけど、東京で一人暮らしを始めたので、なかなか姪と会えなくて、今は姉から送られてくる姪の動画を見て癒されるという日々を送っています。
藤村:Meetとか繋いで話すといいんじゃないですか?
mase:たまにビデオ通話で家族と喋る時に姪と喋ってます。喋るというか、意思疎通できてるのかはわからないんですけど。
藤村:何歳ですか?
mase:2歳です。
藤村:自然言語によるやりとりが可能?不可能?
mase:簡単な言葉ならギリギリぐらいの感じです。
藤村:どんどん通じるようになっちゃうから、今のうちにたくさん話しておかないといけないのかもしれない。
mase:そうですね。
藤村:僕、突然メンズネイルに興味が出たときがあって塗るタイプのものを買ってみたんですよ。
mase:ジェルですか?固めるタイプ?
藤村:普通の塗料みたいな。
mase:マニキュアですかね?
藤村:そうそうそう。
mase:乾かすタイプのやつですか?
藤村:乾かすタイプ。でも難しすぎて、プラモより難しい。
mase:マニキュアのほうが個人的には難しいなと思ってます。ジェルネイルだとちょっとはみ出しても、固めるまでは固まらないので、とれるんですけど、マニキュアだとはみ出るとすぐにとらないといけないのが大変だったり、15分くらい乾かさないといけなかったり。難しくて私はジェルネイルにしました。
藤村:僕は難しい方に飛び込んでしまったということですね。
mase:でもお手軽ではあります。マニキュアのほうがオフするのが簡単なので。
藤村:ジェルネイルだととるのが大変?
mase:ピールオフジェルっていうのがあって、それを一番下に塗っていればペロッと剥がせるんですけど、普通にやると削ったり、アセトンを染み込ませてとるので、爪が傷んじゃうんですよね。
藤村:なるほど、一長一短なわけですね。
mase:そうですね。
わからないことをわかることがRubyKaigiの成果
藤村:maseさん、入社してみてどうですか?楽しんでますか?
mase:そうですね。先週まで研修を8日間ぐらいやってたんですけど、同期の人たちとたくさんお話しできたり、セキュリティ、データベース、TypeScript、Swiftと自分があんまり触ってこなかった分野について広く知識をインプットできて楽しかったです。チームに入ってからは STORES 予約 の仕様、予約の種類がいっぱいあってなかなか理解が難しいなっていうのをすごく実感してるところです。
藤村:STORES 予約の予約タイプとかはディープな世界ですよね。
mase:はい。
藤村:来月RubyKaigi 2024が沖縄で開催されるんですが、maseさんも一緒に行くんですよ。今日はmaseさんやエンジニアとしてキャリアを始めたての人がRubyKaigiに参加する時はどういう気持ちなのかっていうのと、僕からは参加のヒントというか、こういう感じで臨むといいですよみたいな話ができればなと思っています。そもそもRubyKaigi自体は初めてですか?
mase:RubyKaigiは去年オンラインで参加しました。オフラインでは初めてです。
藤村:技術系のカンファレンス自体はRubyKaigi以外に行ったことありますか?
mase:初めてです。
藤村:去年のRubyKaigiのオンライン参加が初ってことですね。
mase:記憶にある限りではそうです。
藤村:RubyKaigiって結構変わったカンファレンスで、オーガナイザーの人が自分が知らない最先端のRubyの作品を知りたい、成果発表みたいなモチベーションでやってるんですよ。だから普通はカンファレンスってもうちょっと仕事に役に立ちそうな話とか、現場でRailsをこうしたとか、チーム開発をこうしたって話が多いんですけど、去年参加しているからわかるかもしれないけど、これは一体何?みたいな話がめっちゃ多いじゃないですか。
mase:そうですね、本当にすぐ置いてかれちゃう、話についていけなくなる感じで、正直理解できた部分は少なかったです。でもRubyの知らない世界を知れて、すごい刺激になりました。
藤村:最初に触れたテックカンファレンスがRubyKaigiっていうのはなかなか。初めて見た鳥を親と思う方式でいくと、かなり極にあるものを見てしまってるなって感じがあるんですけど。そうなんですよね、すぐ置いていかれますよね。
mase:置いていかれました。
藤村:しかも多くのセッションで置いていかれますよね。
mase:そうですね。最後までギリギリ理解できたのは1セッションか2セッションあるかぐらいでした。
藤村:多分みんなそうで、全部わかる人はほぼいないんですよ。なぜならRubyKaigiってRubyを開発している人のカンファレンスで、Rubyについてのカンファレンスなんですよ。Rubyを使ってどうとかいうのよりも、Ruby本体をどう作るかにフォーカスがあるので、プログラミング言語の最新機能とか最新の実装って作ってる人しかわからない人が多いんですよ。だからこそ新しく入るわけで、なので、どれを聞いてもついていけないとか、全部わかる人がいないっていうのはある種カンファレンスとしても狙っているところだと思うんですよね。わからなくていいのだろうかっていう引け目を感じることは一切必要なくて、こんなにわからないことがわかったみたいな、わからないジャンルを知ること自体がもはや成果だと思います。
mase:はい、安心しました。今年もまだ理解できることは少ないんだろうなと思ってて、ちゃんとRubyKaigiに参加してる他の方とうまくお話できるかなって思ってたんで、その話を聞いて安心です。
藤村:本当にすごいセッションだと終わった後に「何だったんですかね」ってなるんですよ。みんなわかってるふりすらしない感じなので、そこは安心していいと思います。
気になるキーワードやトピックを予習しておく
藤村:タイムテーブルは見ましたか?
mase:まだ見てないです。
藤村:予習っぽいことをするのであれば、タイムテーブルを見て、わからない用語がたくさん出てくると思うんですけど、それぞれ一体ざっくり何なのかなっていうところまで調べておくとはかどっていいですよ。
mase:なるほど。
藤村:例えば、今年は「Wasm」って言葉がいっぱい出てくるんです。Wasmってご存知ですか?
mase:わからないです。
藤村:そんなにみんながみんな知ってるトピックではないと思うんですけど、新しいコンピュータの技術としてあるんですよ。これが何なのかをChatGPTに「Wasmって何ですか」と聞いたらばーって説明してくると思うんですが、その説明がわからなかったりする。説明の中でわからない用語をChatGPTにさらに聞くと、もっと簡単に説明してくれるので、それで当たりをつけて見取り図を脳内に用意しておけば、この技術のこの話はこことつながってるのかとわかるので、いいと思いますね。
mase:ChatGPTとたくさんお話しして準備します。
藤村:セッションを聞いてる途中でも聞くと便利かもしれない。僕も最近新しいことを調べるときは全部ChatGPTに聞きまくってますね。なので、それがいい気がします。
mase:私もミーティング中にわからない単語がたくさん出てくるので、STORES 予約 の中のGitHub Copilot Chatによく聞いてます。
藤村:あれは便利ですよね。
mase:便利です!ちゃんと答えてくれて参照先もわかるので、たどって見るんですけど。ミーティング中にそれを見ていたらミーティングにだんだん置いていかれちゃいます。
藤村:あるある。あとはスピーカーの人に感想を伝えるとすごく喜ばれると思います。すごい人たちが登壇しているので、話すのはめっちゃ緊張するんですけど、「社会人としてはまだ1年目なんですけど、今回の話すごく面白くて刺激を受けました」って全部わかってなくても言うとすごく喜ばれると思います。ぜひ懇親会とか会場でぶらぶらしてる時に「この話面白かったな」というのがあったら話しかけるというのもぜひやってもらえると。
mase:やってみます。コミュニケーションをできるだけたくさん取れたらいいなと思っているので。
藤村:予習の話に戻るんですけど、このトピックが多いなみたいなのがあるんですよ。今年はWasmの話が多くて、去年はParserの話が多いとか。今年もParserの話は結構あるんですけど、もし余裕があったらParserなり、Wasmなりの簡単な本やまとまったドキュメントでちゃんと勉強してみるっていうのも広がっていいと思います。
mase:はい。
藤村:ちなみに、例えばParserとかWasmのことを理解したからってすぐに仕事に使えるわけでは全然ないんです。RubyKaigiで扱われるトピックってコンピュータの中でも基礎技術に近いものが多いんですね。僕らが書いてるのは応用というか、プログラミング言語という道具、Rubyが用意されていて、それを使って僕らはものを作ってるじゃないですか。それをアプリケーションって言ってるんですけど、もっとその下にあるプログラミング言語自体とか、プログラミング言語自体の中でも部品に分かれていて、更に基礎的な部品や応用的な部品がある。RubyKaigiはその基礎の部分の話が多いので、なかなか目の前の仕事の何に役に立つんだろうっていうのが謎な面はあるんですけど、コンピュータのことをよく理解してやらないといけない仕事にだんだんなってくると、役に立つことが多い、多いといいなみたいな感じで勉強してます。
Appleの社長だったスティーブ・ジョブズの有名なスピーチがあって”Connecting the Dots”*2って話をしてるんですけど、彼は学生の頃タイポグラフィを自主的に勉強していて、結果的にAppleって字のレンダリングが綺麗とか、そういうところでも評価されていたりするわけですよ。勉強したことが将来何の役に立つのかわからないけど、それがつながると何か大きな今までできなかった成果につながるっていうような話なんですね。
多分RubyKaigiでやることも、将来にもしかしたら役に立つかもしれないこととか、もしかしたら今回のRubyKaigiでmaseさんが突然Wasmに目覚めて、Wasmに取り組むエンジニアになってしまうかもしれないじゃないですか。それはそれで自分の情熱が傾けられるところが見つけられて、めちゃ素敵なことだと思うんで、そういう何かネタを仕入れにいく感覚でいくと、RubyKaigiは価値がある時間になるんじゃないかなと思いますね。
mase:そうですね。
藤村:一旦興味を持ってみる。見てみて将来何の役に立つかわからないし、自分と今何の関係があるかわかんないけど、面白そうって見てみるっていうのが楽しみ方としてはめっちゃいいような気がしますね。
mase:今はRubyに対して何があるのか、Wasmもそもそもあることすら知らなかったので、そういうキーワードだったりを仕入れて、自分の興味のあるところを見つけられたらいいなと思いました。
藤村:そうですね。それで新しく興味を持つことができたら、一番RubyKaigiらしい楽しみ方のような気がします。
一番聞きたいセッションを万全な状態で聞くために
藤村:maseさんからRubyKaigiにたくさん参加してたり、CTOをやったり、Rubyエンジニアとして長い間仕事をしている僕に聞いてみたいことがあったらと思ったんですが、なにかありますか?
mase:技術カンファレンスやRubyKaigiでコミュニケーションを取るときに、どういうお話をしているのかに興味があります。
藤村:スピーカーの人には「めっちゃ面白かったです、ありがとうございました」っていうので、そこから話が広がったり広がらなかったり。「そういうのやってるの?」みたいな感じで話が広がったりすることが多いし、おしゃべりな人が多いので、1個きっかけがあると盛り上がりがちだったりしますね。あとは同世代の人とかとお話するのもいいですよね。
mase:技術の話で盛り上がるんですか?セッションの部分で盛り上がったりみたいな感じなんですかね?
藤村:廊下で立ち話が盛り上がるっていうのがカンファレンスあるあるで、セッションを聞かないで廊下でずっと技術のディスカッションをしてる人々っていうのが名物的にいるんですよ。トーク詰め詰めで脳の負荷が高いというか、面白いんだけど、難しいトークが多いので。全部聞けたらいいんですけど、体力的に難しいので程よく休みを取るほうがいいというのが僕の考えです。
mase:なるほど。
藤村:休んでブラブラしてるときに友達とばったり会って盛り上がるみたいなことが起きがちですね。Rubyコミュニティに限らずですけど、カンファレンスで会って話して、別に技術の話じゃなくても、同世代とか何か接点があったら盛り上がると思うんですけど、それで同僚でもなく、学生時代の友達でもなく、新しい友達ができること自体がいいことだと思うから、あんまり技術の話ばっかりすればいいってものではないと思いますね。社会人になるとなかなか友達をつくるのが難しいので。
mase:もう実感してます。
藤村:共通点のある知らない人と会うって感じなので、話すトピックは雑談でもいい、沖縄すごいですねみたいな。そういうのを素朴に話せば大丈夫だと思います。みんながみんな技術のディスカッションを一日中していたいわけではない。そういう人が一般の空間に比べると顕著に多い空間ではありますし、技術の話は盛り上がりがちなんですけど、何でもいいと思います。
mase:何人かと仲良くなれたらいいなと思います。
藤村:気楽に。あとはhogelogさんとか僕とかは知り合いがそこそこいるので、話してみたい人がいれば紹介するので言ってください。
mase:嬉しいです。全部のセッションは出てないって仰ってましたが、どれぐらい出るんですか?一日に半分くらいですか?
藤村:僕は6割から7割ぐらいですかね。体調が万全な時で。
mase:私は去年オンラインで参加したときに全部聞いてたんですけど、3日目あたりで疲れと脳みそがパンクしそうで。オンラインで参加してると、オフラインで参加してる人が全部出ていないっていうのもわからなかったんで、全部見てたらすごい疲れたっていう記憶が今蘇ってきました。
藤村:特にオフラインだと情報量も多い。しかも行ったことない場所で知らない人とたくさん過ごすので、そこそこ刺激とストレスがあると思ってるんですよ。それで頭が爆発しそうなコンテンツを朝から晩までずっと聞いていたら、そりゃ体はもたない。体はもたないし、一番聞きたいセッションを万全な状態で聞けないので、ほどよく休息を取るのは重要だと思ってますね。
mase:だいたい6、7割ぐらいで。
藤村:もうちょっとちゃんと聞いてる人も多いと思いますけど、僕は真面目に聞く分、全部理解しようとして、頭をフル回転して聞くので、燃費が悪いタイプのRubyKaigiの楽しみ方としてますね。なので6、7割ぐらいしか楽しめない感じになってます。
mase:自分が聞きたいセッションをいくつかピックアップして、それを万全に聞けるような体制で挑もうと思います。
藤村:そうですね。RubyKaigiは現場が盛り上がっていて、体温が高い。現場に行くと「おお!」ってなると思うんで、楽しんでもらえると嬉しいですね。
mase:めちゃくちゃ楽しみです。
藤村:ということで、今月入社して来月RubyKaigiに一緒に行くmaseさんとRubyKaigiのお話をしました。maseさん、ありがとうございました。
mase:ありがとうございました。
藤村: #論より動くもので感想をお待ちしてますので、ぜひポストをお願いします。あとは、お便り募集フォームを作ったので、お便りをいただけるとお便りコーナーのタイムができるのでぜひよろしくお願いします。そして一緒に働くエンジニアもめちゃくちゃ募集しています。STORES はRubyを書くにはとても面白い場所になっているので、ぜひRubyKaigiで直接お声かけください。よろしくお願いします。ということで、論より動くもの.fmを終わります。ご機嫌よう。(完)
RubyKaigi 2024でお会いしましょう
STORES はNursery SponsorとしてRubyKaigi 2024に協賛していて、たくさんのメンバーでRubyKaigi 2024に参加します。 ぜひ STORES のメンバーと交流してください。ブースでもお待ちしております!
