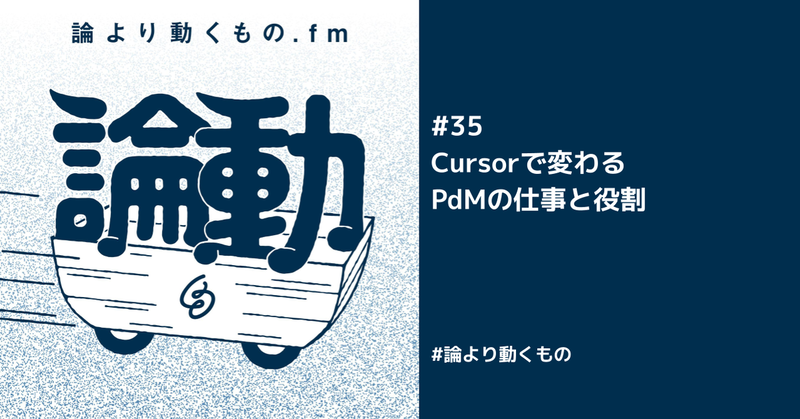
CTO 藤村がホストするPodcast、論より動くもの.fmの第35回を公開しました。今回はプロダクトマネージャーの西岡と、LLMを使ったプロダクトとAIとPdMの仕事について話をしました。
論より動くもの.fmはSpotifyとApple Podcastで配信しています。フォローしていただくと、新エピソード公開時には自動で配信されますので、ぜひフォローしてください。
最近気になる音楽
藤村:こんにちは、論より動くもの.fmです。 論より動くもの.fmは STORES のCTO 藤村が技術や技術じゃないことについてざっくばらんに話すポッドキャストです。今日はこの春からICR(Intelligent Commerce Research)というAIプロダクトを作るチームで日々一緒に働いてる西岡さんに来てもらってます。西岡さん、こんにちは。
西岡:こんにちは。
藤村:面白い自己紹介をお願いします。
西岡:ポッドキャストを聞くのがすごく好きで、よく散歩しながら聞いてるんで、こうやって出ると緊張しますね。
藤村:でしょ。
西岡:急に藤村さんがそういうトーンになったから余計緊張しました。さっきまで普通に喋ってたのに。
STORES には、この7月で丸7年いて、ずっとプロダクトマネージャーをやってます。STORES は複数プロダクトがあって、最初はネットショップを担当していました。その後、予約サービスを提供するCoubicがジョインしてからは、Coubicの担当になり、4年弱ぐらい STORES 予約 のプロダクトマネージャーをやってました。今年の年始から1ヶ月くらい育休をもらって、復帰して、3月からICRでプロダクトマネージャーをやっています。よろしくお願いします。
藤村:よろしくお願いします。昼飯のときに、最近亡くなったJJJさんの話をしたんですけど、好きな音楽も被っていそうだなと思っているんですが、最近なんか面白い音楽ありました?
西岡:友達に教えてもらったやつですけど、Texas 3000っていうバンドがいて。3人組のグループで、アメリカ人、日本人、中国人っていうバンドで90年代インディロックみたいな感じです。久しぶりに僕もそういうのを聴いたんですけど、ライブがむちゃくちゃいいっていう友達に聞いて、来週月曜にライブを見に行く。楽しみにしているバンドのひとつです。
藤村:ライブはどこですか?
西岡:FEVERっていう...
藤村:代田橋かな。
西岡:そうです。
藤村:いいなぁ。
西岡:僕も初めてそこ行くんで、ライブハウスの名前は知ってて、すごい良さそうな箱で。
藤村:めちゃいいです。音もいいし、居心地もナイスな名スポットですね。
LLMプロダクトをリリースして感じたこと
藤村:この話のままあと20分終わってしまいそうなんですけど、仕事っぽい話にすると、最近何してるんですか?
西岡:今はICRというチームでAI、LLMを使った新規プロダクトを作っていて、エンジニア3人とPdM1人の4人チームでやってます。5月の最初にベータ版として一部のオーナーさんに使ってもらえるプロダクトを出して、そこから2、3週間ぐらい経っているところです。LLMを使ったプロダクトをリリースするのが STORES では初めてなので、利用状況を見ながら、LLMの使い勝手というか、どういうふうに進化させていくか、どういうふうに改善を回していくのかを考えてます。
藤村:やりたいことが無限にありますよね。
西岡:そうですね。今までできないと思っていたことも、LLMだとできるようになることが多すぎて、かつ日々アップデートがされていく。やりたいことはすごくあるんですが、まだまだ方法論というか、僕らのチーム内でもそこまでカチッと固まってなかったりとかするので、地面がなかなか見えない中で進んでいってる感覚ですよね。
藤村:実際にLLMを使ったプロダクト、小さいものでもリリースしてみると、なんか感覚変わりません?これできるんだみたいな。
西岡:アイデアベースではいろんなことができそうだねっていう話を4月はしてたんですけど、実際に出てみると、思ったよりできない部分もある。料理しないままで素材の味だけでいったら、そんなに美味しくなかったみたいなこともあったり。とはいえ違った方向性への進化もあって、ユーザーの反応を見ながらチューニングしていくのは、LLMプロダクトの醍醐味だと思うし、それをやっていきたい、楽しみって感じです。
藤村:いやー、早くマジックを起こしたいですね。
西岡:そうですね。
v0でプロダクト開発のスピード感が変わった
藤村:今は西岡さんも途中からコードを書くようになったじゃないですか。元々プログラミングってやってた?
西岡:合間合間で1ヶ月ぐらい学校に行って1日10時間コード書くみたいな、Ruby on Railsで簡単に動くTwitterみたいなもののチュートリアルを作ることは、数年前に何回かやったことあるんですけど、業務レベルでエンジニアとしてプログラミングをしたことは全然ないです。
藤村:西岡さんのICRにおけるファーストプルリクエストは何だったっけ?
西岡:何だったっけ...戻るボタンをつけるとかかな?
藤村:そうそう、そういう感じだった。
西岡:あ、バイブコーディング歴の一番最初は、一緒に働いてるエンジニアの人に言ってもらったんですけど、新しい画面が一つ必要になって、その画面をどうしよう、要件を考えるかという話をした時に、その方が「v0で西岡さんが作っちゃえばいいんじゃない?」って言ってくれて。実際半日、一日ぐらいでそれなりにものができて、それを藤村さんに引き継いでバックエンドを書いてもらった経験が一番最初ですよね。
藤村:それだ!その辺で僕らエンジニアが調子に乗って西岡さんにコード書いてもらっていいんじゃないかみたいな。
西岡:そうそうそう、アサインがされるようになってしまった。
藤村:Cursorに雰囲気で頼めば、雰囲気で出してくれるんで大丈夫ですみたいな。
西岡:その最初のv0はすごい良かったなと思ってて。僕らのチームにはデザイナーがいないのでエンジニアとPdMでデザインをしている体制なんですが。今までの進め方だと僕が仕様書を書いて、それをデザイナーに依頼をして、社内のレビューを通って1、2週間ぐらい経って、デザインが固まってからエンジニアが実装するフローになってました。そのフローがv0を使うことによって、1、2週間かかってたものが1日、2日で、バックエンドも含めてできるようになった体験は、僕にとっても衝撃的でした。AIを使ったプロダクト開発として、今後スタンダードになっていく動きなのかなって。
藤村:うちはビジュアルデザインへの要求が高い会社だと思うので、そういう面もあるんだろうけど。にしても、バイブコーディングでできたもののクオリティが「こういう商用サービスでもあるよね」みたいなクオリティで出てくる時ありますもんね。
西岡:そうですね。今作ってるもの自体もそこまで複雑な機能もないので、耐えられるかなっていう感じです。
藤村:昔だったら依頼しないと出てこなかったクオリティではあるからな。
西岡:うんうん。それが体感できたのがすごくよかったです。スピード感がすごい増したなって感じがします。
PdMのCursorの使い方
藤村:西岡さんが使っているのはCursorですよね?
西岡:Cursorです。
藤村:Cursorにどんなふうにお願いしてるんですか?
西岡:エラーが出たら画像を貼って「エラー出たよ」って言ってます。エラーのテキストも読まずにすぐ、エラーの画像を貼るんで。その作業がめっちゃ早いですからね。0.5秒くらいです。
藤村:チームメイトの中野さんが言うところの反知性主義でしょ。
西岡:何も考えないでその作業をやってます。藤村さんが言ってましたが、CursorのLLMが返してくる内容は、自分の依頼内容が不十分なので、当たる当たらないがあって、ガチャ要素がある。だから当たるまで、ローカルで正常に動くまで、Cursorに指示しまくる。LLMの無駄遣いをしてる感じがしますけど。
藤村:本当はこういうふうな書き方でいろんな指示を追加してマークダウンでこういうフォーマットでやるといいみたいなのがあるんですけど、我々はガチャを引きまくるという、知性がなさすぎるタイプのバイブコーディング。
西岡:そうですね、僕はそういう感じでやってしまってます。
藤村:大丈夫だろうか、僕が提唱してますけど。
西岡:エンジニアの基礎スキルがあると、もう少し組み立てて構造的に要件を伝えることができると思うんですけど、そこはノリでやらせてもらっています。
藤村:僕も別のプロジェクトでコードを書いてる時は、「出てきたものを受け入れる心が重要」みたいなノリでやっていて、自分の意図とかじゃないんですよ。「ありがたく出てきたものを使わせていただいて、それを僕らの方で調整させていただく」気持ちでやってます。俺よりプログラミングAIの方が上手いんだから、もう素直に従った方がいいだろうって思ってます。
西岡:なるほど。藤村さんでもそれやったら仕方ないですよね。
藤村:あのスピードでコード書けないですもん。100%負けてるんですよ、だからもういいやと思って。でもそれも出てきたコードの良し悪しが、さまざまな側面から自分が評価できるから、できてるっていうのもあるかもしれないですけど。
西岡:そうそう、僕は基礎知識がないからそこができないなと思っていて。前に簡単に見えるタスクを渡してもらってやったら、diffが200行くらいあって、僕は1行も意味わからないけど、ローカルで動いたからプルリク投げたら、藤村さんにほぼほぼ全直ししてもらうっていう。申し訳ないと思いながらプルリクのレビューを見てたんですけど。
そういう意味ではPdMがバイブコーディングする限界もあって、複雑なものや、出てきたものへのフィードバックや評価は正しくはできないから、そこばっかりやっていても仕方がないかなって気はしますけど。
藤村:とはいえ、今までは人に頼まないといけなかったことが、自分でできるようになっちゃったわけじゃないですか。どうですか?仕事の喜びというか、やっていて気分はどうか聞いてみたい。
西岡:それはめちゃくちゃいいですよね。単純に人としてできることが増える喜びとか、今までは文言変更すらエンジニアに頼まないとできなかったものを、ささっと色変更やリンク変更ができるのは、個人的には楽しいし、生産性が上がったところかなと。
あとは仕様理解やデータベースの構造とか、「これどうなってるんだっけ」みたいなところも、基本的にはgit pullして、Cursorに仕様を聞いて答えてもらったり、該当の箇所を教えてもらえたりするので、開発におけるコミュニケーションもやりやすくなったなって感じます。
藤村:西岡さんはその使い方をしてますね。説明ツールとしてリポジトリとCursorを使う。
西岡:そうですね。それは今のプロダクト以外の、社内の別プロダクトの仕様理解でも使ったりしてます。
藤村:うん。前はドキュメントが必要だったけど、今はコードをCursorに読んで説明してもらえばいけるみたいな。
西岡:そうそうそう。
藤村:便利ですよね。
西岡:コードがSingle Source of Truthなので、それを元に正しく理解することができるようになったのが嬉しいです。
PdMの役割の変化
藤村:我々エンジニアやプロダクトマネジャーの仕事のあり方も日々新しく発見されていく感じがありますよね。
西岡:そうですね。よく言われることですけど、PdMはLLMに載ってない情報をいかに取得するか、LLMで返ってこない一次情報をいかに取得して、それを元に意思決定するか。ユーザーの一次情報を獲得するための動きは、その中で重要になってくるなと思ってます。
藤村:AIだとなかなか代替が難しそうですね。
西岡:そうそう、そこはAIがまだできないところなのかなと思ってます。
藤村:西岡さんのユーザーインタビューに同席してて思ったけど、やっぱり聞き出す力というか、隠されていたコンテキストを見つける力が、プロダクトマネジャーの特殊能力なんだなと思ったんですけど。それは人間ならではのコンテキストの詰め込み方がゆえなんだろうなと思いましたね。
西岡:同じ情報を受け取っても、解釈って人それぞれだと思うので、どのコンテキストの話を引っ張って深掘りしていくか、どこにイシューがあるんだっけみたいなところを探す能力っていうのはより求められる感じはします。
藤村:そうですね。面白い時代ですよね。
西岡:PdMは役割が大きく変わるだろうなと。今まで、この5年、10年って、組織が大きくなることが成長の一つの方程式だったと思うんですね。調達して、ビジネスチームやプロダクトチームを大きくして、コンパウンドで複数プロダクトを作っていくぞみたいなゲームから、もう少しスモールチームで、小回りが効くような形で開発をしていくフェーズに変わっていく時に、PdMとして求められることが大きく変わっていく感じはします。
藤村:どうなるんだろうって不安もさることながら、前線で日々何かを作っていると、これからどうなるかとかよりも、今、目の前のこの機能が賢くなさすぎるから、なんとかしたいんだけどみたいなのが大きいですよね。
西岡:そうですね。それが一番大事だと思います。
コンパウンドって言わなくなったよね
藤村:かつてはみんなコンパウンド、コンパウンドって、SaaSの会社の人は経営戦略みたいに言ってたじゃないですか。このAIエージェント時代になって、みんなあんまり言わなくなったのかって。
西岡:そうそうそう。
藤村:隠してますよね。
西岡:明らかに言わなくなったんですよね。
藤村:ぶっちゃけまだよくわからないってことと、隠しているのが2個あるなと思って。
西岡:なんか言わなくなったぞっていう空気感を察して、ちょっと時代遅れ感が出ちゃうのか、あんまり言わなくなりましたね。
藤村:「コンパウンド」も言わなくなったし、エージェントでどうするのが我々の戦略だみたいなことを、バンってみんな言わなくなってるのが、みんな手の内を探り合っているんだろうなって思って。
西岡:確かに。
藤村:ちょっと面白い。
西岡:海外が先行しすぎてて、あんまり日本でAIエージェントを活用して実績がすごく出ている状況ではないですよね。やっぱ海外のプロダクトがAI機能とかLLMをうまく使って機能リリースを毎月のようにバンバンやってる中で、日本としてそこまで打ち出せて、実際LLMを組み込んだ開発とかもしてるところも少ないと思うんで、僕らまさにそこのフェーズですけど、そこはやっていきたいですね。
未来の STORES ?
藤村:未来の STORES を作れそうな気がします、どうやって作るか全くわからないけど。
西岡:そうそう、どうやって作るか全くわからないけど。今のプロダクトはAIネイティブなプロダクトではないから、そこに対する焦りというか、まだ見ぬAIネイティブなアプリケーションが出てきたときに、ネットショップを作る、予約サイトを作るっていう体験がかなり変わってくると思うので、負けないように、僕らとしてもできるだけ、AIネイティブに寄せていかないとダメかなと感じています。
藤村:買う方、消費者側も変わるでしょうね。OpenAIはハードウェアを出すって言ってましたね。
西岡:そうですよね。ioを買収して、プロトタイプに感動したって記事に書いてて、どんなプロトタイプだったんだろうと気になってます。
藤村:まあでも最前線で、じたばたできるのは楽しいですね。
西岡:まだそこまで答えがないから、わからないながら、霧の中を走り回るみたいな感じで。
藤村:とりあえず全部ドアを開けるしかないみたいな。
西岡:そうそう。とはいえユーザーが近くにいるから、ユーザーのフィードバックを元にプロダクトを作っていくのが一番楽しいかなと思います。
藤村:そんな感じで西岡さんと僕は、Intelligent Commerce Researchの略でICRなんですけど、将来の賢いコマースの在り方を探そうと今やっていて、とっても楽しくやってます。ということで今日は、藤村と一緒にバリバリプロダクトを作っているプロダクトマネージャーの西岡さんに来てもらいました。西岡さん、ありがとうございます。
西岡:ありがとうございます。
藤村:論より動くもの.fm、今回は終わろうと思います。#論より動くもので感想を教えてください。皆さんごきげんよう。(完)
STORES ではエンジニアを募集しています。論より動くもの.fmを聴いて、少しでも STORES に興味を持たれた方は、ぜひカジュアル面談でお話しましょう!
